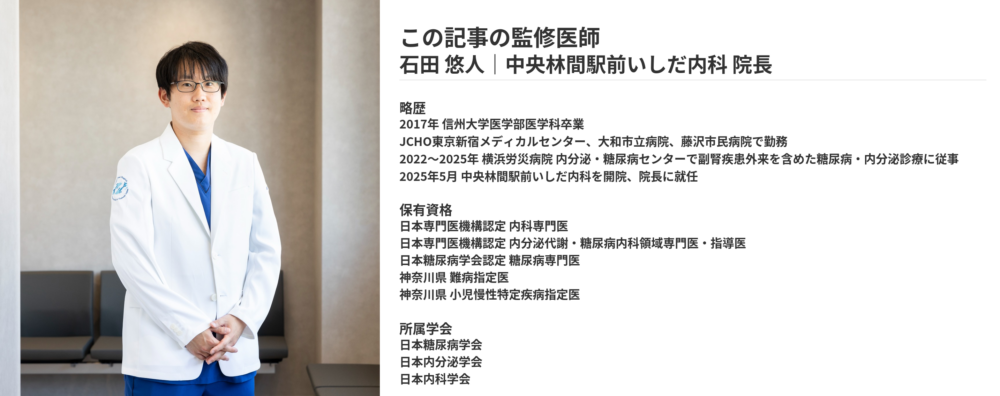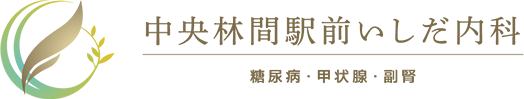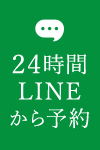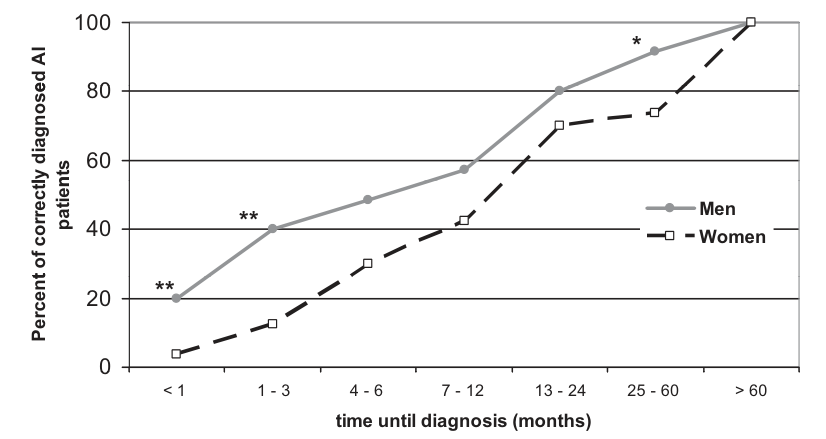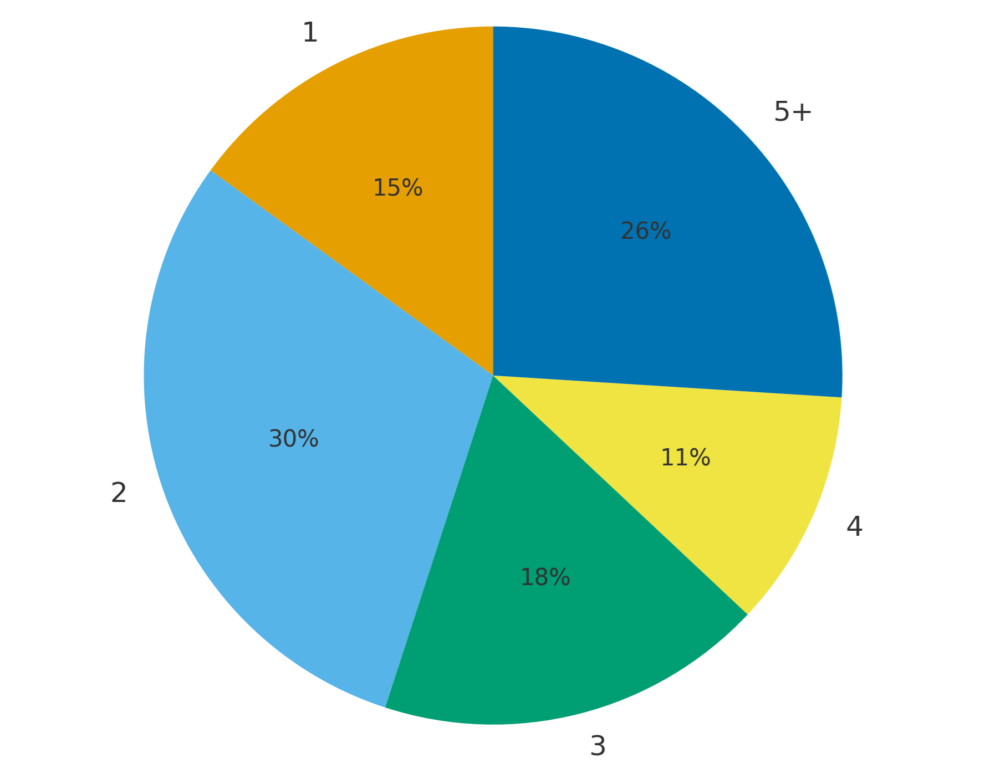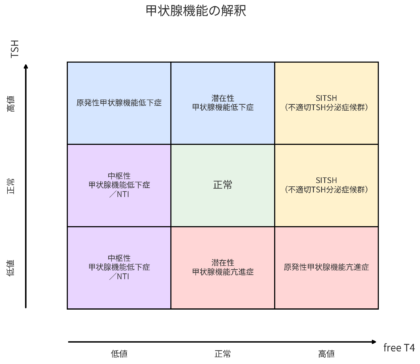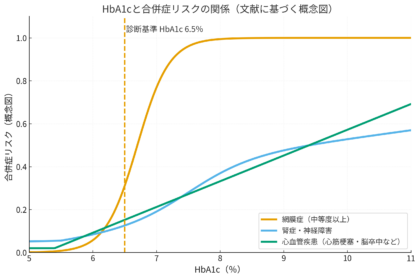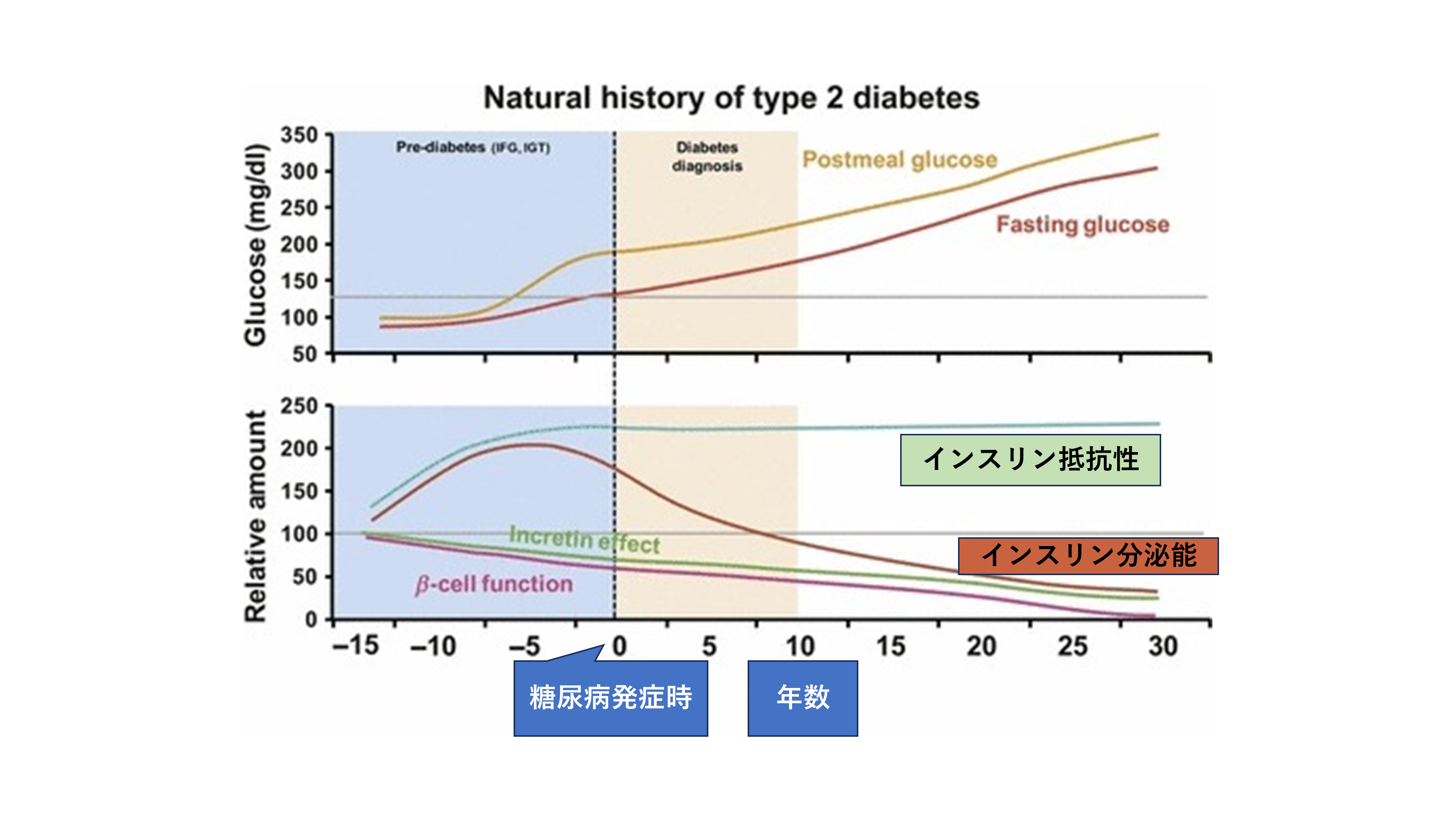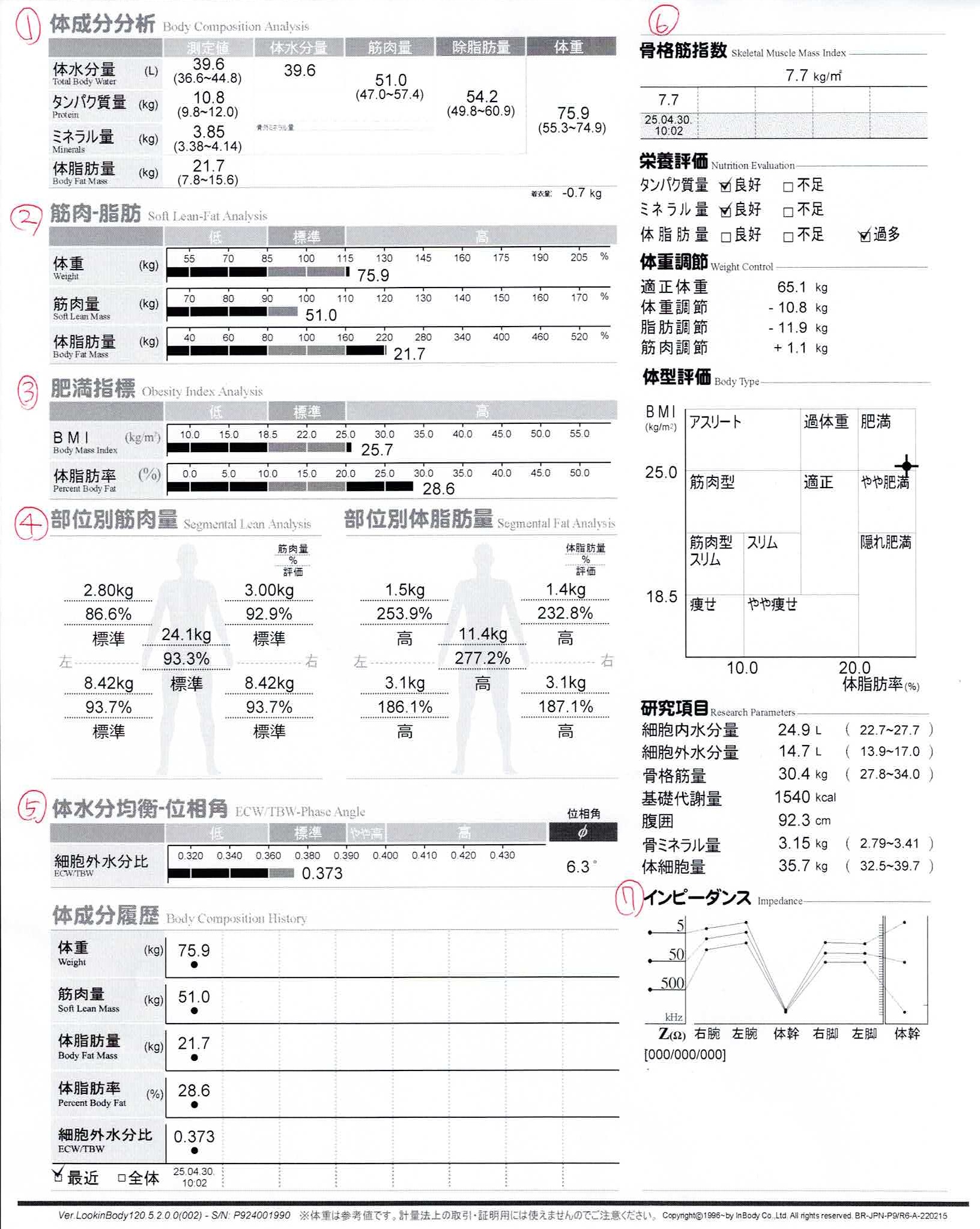家庭で測る血糖値は「どれくらい正確?」― SMBGとCGMの精度とMARDをわかりやすく解説 ―


家庭で行うことのできる血糖測定には、**SMBG(指先血糖測定)**と、**CGM(持続血糖測定)**があります。
血糖値の基準として用いられるのは、病院で採血して測定される静脈血の血漿グルコースです。これが、いわば「基準となる血糖値」です。しかし、この検査は病院でしか行えません。
そこで、日常生活の中でも血糖値を確認できるように開発されたのが、SMBGとCGMです。
SMBGもCGMもとても便利な方法ですが、どちらも「病院で測る血糖値」とまったく同じになるわけではなく、ある程度の誤差があります。
この記事では、「家庭で測る血糖値はどれくらい正確なのか?」という点について、できるだけ分かりやすく解説します。
血糖測定の「ズレ」を表す言葉:MARDとは?
血糖測定器の正確さを表す指標のひとつに、**MARD(マード:平均絶対相対誤差)**があります。
MARDとは、
👉 測定された血糖値が、基準となる血糖値から平均して何%ずれるか
を示した数字です。
たとえばMARDが5%であれば、
本当の血糖値が100 mg/dLのときに、平均して±5 mg/dL前後のズレが生じる、という意味になります。
ここで大切なのは、「毎回必ず±5になる」という意味ではないということです。
MARDは、「長く見たときに、どれくらい当たりやすいか」を示す目安と考えると分かりやすいでしょう。
市販の指先血糖測定器には国際基準があります(ISO15197)
市販されている指先血糖測定器(SMBG)は、ISO15197という国際的な精度基準を満たすことが求められています。
この基準では、
・血糖値が100 mg/dL未満のとき:±15 mg/dL以内
・血糖値が100 mg/dL以上のとき:±15%以内
に、95%以上の測定値が入ることが求められています。
少し難しく聞こえますが、これは
👉 「低血糖域を含めて、少なくとも一定以上の精度を満たしていることが確認されている」
という意味です。
ISO15197は、市販SMBGの最低限の品質ラインと考えるとよいでしょう。
一方で、CGMは連続測定装置であり、指先の一回の値とは性質が異なるため、ISO15197 のような一回値の精度基準ではなく、別の評価指標(MARD/エラーグリッドなど)が用いられます。
SMBG(指先血糖測定)の誤差はどれくらい?
指先血糖測定器のMARDは、機種にもよりますが、おおよそ5〜10%程度と報告されています。最近の機種では、条件が良ければ非常に正確な値が出ることも多く、「その瞬間の血糖値」を知る方法としてとても信頼性が高い検査です。
一方でSMBGは、
・手に糖分が付いている
・指を強く絞って採血する
・指先の血流が悪い(冷え、脱水など)
といった条件の影響を受けやすく、実際より高く出たり、低く出たりすることがあります。
つまりSMBGは、
✔ うまく測れたときはとても正確
✔ ただし測り方や状況に左右されやすい
という特徴を持っています。
CGM(持続血糖測定)の誤差はどれくらい?
CGMは、皮下に入れた小さなセンサーで、24時間自動的に血糖の動きを測り続ける方法です。
CGMは指先の血液ではなく、**間質液(細胞と細胞の間を流れる液体)**中のグルコースの変化をもとに血糖値を推定しています。
最近のCGMでは、MARDはおおよそ8〜10%程度と報告されています。
例えば、フリースタイルリブレ2は約9%前後、Dexcom G7は約8%前後とされています(試験条件により多少異なります)。
CGMには、
✔ 自動で測定される
✔ 血糖の「流れ」や「傾向」が分かる
✔ 夜間や無自覚低血糖に気づきやすい
という大きなメリットがあります。
一方で、間質液のグルコースを測っているため、血糖値が急に上下したときには、実際の血糖より少し遅れて表示されるという性質があります。
では、SMBGとCGMはどちらが正確なのでしょうか?
この質問の答えは、実はとても大切で、
👉 「いつの血糖値を知りたいか」
👉 「どんな目的で使うか」
によって変わります。
-
血糖が安定していて、正しく測定できた1回の値なら
→ SMBGの方が血漿血糖に近いことも多い -
日常生活の中で、何も考えずに使い続けた場合なら
→ CGMの方が安定して全体を反映しやすい
という関係にあります。
実際におすすめされている使い分け
現在の糖尿病診療では、次のような使い分けが基本になっています。
📡 普段の血糖管理はCGM
・血糖の動きや傾向を知る
・低血糖や高血糖に早く気づく
・生活習慣を振り返る
🩸 安全確認はSMBG
・症状とCGMの値が合わないとき
・低血糖が疑われるとき
・急に数値が大きく変わったとき
つまり、
👉 CGMで日常を見守り、SMBGで確認する
という役割分担が、もっとも安全で現実的な使い方です。
まとめ
・家庭で測る血糖値には必ず誤差がある
・SMBGは「うまく測れた一回」に強い
・CGMは「日常全体の流れ」に強い
・両者は競合ではなく、補い合う存在
血糖測定は「数字を当てること」だけが目的ではありません。
安全に、早く気づき、生活に活かすことが最も大切です。
SMBGとCGMを上手に使い分けることで、より安心で質の高い血糖管理が可能になります。