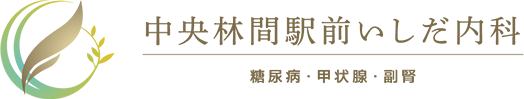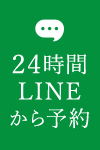糖尿病には色々なタイプがあります
一般的に糖尿病というと、2型糖尿病を指すことが多いと思います。
しかし実際は、一口に糖尿病といっても、様々なタイプの糖尿病があります。
以下に糖尿病の成因(≒糖尿病のおおもとの原因)分類を示します。
Ⅰ. 1型(膵β細胞の破壊。通常は絶対的インスリン欠乏に至る)
A.自己免疫性
B.特発性
Ⅱ. 2型(インスリン分泌低下を主体とするものと、インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を伴うものなどがある)
Ⅲ. その他の特定の機序、疾患によるもの
A.遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの
(1)膵β細胞機能に関わる遺伝子異常
(2)インスリン作用の伝達機構に関わる遺伝子異常
B.他の疾患、条件に伴うもの
(1)膵外分泌疾患
(2)内分泌疾患
(3)肝疾患
(4)薬剤や化学物質によるもの
(5)感染症
(6)免疫機序によるまれな病態
(7)その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことの多いもの
Ⅳ. 妊娠糖尿病
(清野裕ら. 糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告(国際標準化対応版): 糖尿病 55: 485-504, 2012)
・・・なんのことだかチンプンカンプンかもしれません。
これをある程度理解するには、インスリンを理解する必要があります。
インスリンとは、膵臓のβ細胞というところから分泌されるホルモンです。血糖値を下げる唯一のホルモンがインスリンであり、血糖値を下げる役割の大部分をインスリンが担っています。よって糖尿病(=血糖値が上がりやすい状態)の主要な原因として、インスリンの分泌が少ない、もしくはインスリンが効きにくい、ということが考えられます。
これを元に考えると、
1A型糖尿病=膵β細胞が自分の免疫で破壊されて、インスリンの分泌が少なくなる状態
1B型糖尿病=膵β細胞が(免疫以外の)何らかの理由で破壊されて、インスリンの分泌が少なくなる状態
ⅢA(1)=遺伝が原因で膵β細胞の機能が低下し、インスリンの分泌が少ない状態
ⅢA(2)=遺伝が原因で、インスリンが効きにくい状態
ⅢB(1)=膵臓が何らかの原因でダメージを受けて(炎症や癌など)、インスリンの分泌が少なくなる状態
というように、糖尿病の成因分類に書いてあることが何となく理解できるようになります。
糖尿病の成因が何であるかによって、予後(これからどうなるのか)や、合併症や、治療が変わってくるので、成因分類は重要です。
例えば1型糖尿病の中の緩徐進行1型糖尿病というものは、2型糖尿病と見分けがつきにくいと言われています。緩徐進行1型糖尿病では、インスリンの分泌が(2型糖尿病と比較して早期に)少なくなっていくため、2型糖尿病と同じような薬での治療を行っていると、いつまで経っても血糖値が改善しないことなどがあります。
また、ⅢA(1)の中のMODY(若年発症成人型糖尿病)のうちのMODY1や3は、SU薬という種類の薬が非常に良く効くことが知られており、MODY2は血糖値は糖尿病の水準であるものの、薬の治療は不要とされています。これらは2型糖尿病の標準的な治療・予後と大きく異なります(MODYについてはいずれ記事にしようと思います)。
一般的な内科の先生は、糖尿病の治療はある程度できますが、成因にまで注目している先生は少ないと思われます。大多数の糖尿病の方は2型糖尿病であるため、結果的には概ね何とかなっているケースが多いように思いますが、糖尿病は糖尿病内科の先生に診てもらった方がより安心かもしれません。
当院では、糖尿病の成因分類も含め、きめ細やかな分析・治療を心がけていきます。